串田孫一-夜の写真闇の文学-
からまつのはやし-詩三編-
 カラマツの林(栗駒山駒ノ湯上)
カラマツの林(栗駒山駒ノ湯上)
カラマツの花(栗駒耕英地区)
かわいらしい葉(栗駒耕英地区)
からまつの詩を3編
からまつ
串田孫一
からまつはいま 雪のなか
あの秋のこがね色
あの春のあの匂い
落葉松
北原白秋
三
からまつの林の奥も
わが通る道はありけり。
霧雨のかかる道なり。
山風のかよふ道なり。
四
からまつの林の道は
われのみか、ひともかよひぬ。
ほそぼそと通ふ道なり。
さびさびといそぐ道なり。
五
からまつの林を過ぎて、
ゆゑしらず歩みひそめつ。
からまつはさびしかりけり。
からまつとささやきにけり。
六
からまつの林を出でて、
浅間嶺にけぶり立つ見つ。
浅間嶺にけぶり立つ見つ。
からまつのまたそのうへに。
七
からまつの林の雨は
さびしけれどいよよしづけし。
かんこ鳥鳴けるのみなる。
からまつの濡るるのみなる。
(一,二省略 三~七まで)
落葉松
野上彰
落葉松の 秋の雨に
わたしの 手が濡れる
落葉松の 夜の雨に
わたしの 心が濡れる
落葉松の 陽のある雨に
わたしの 思い出が濡れる
落葉松の 小鳥の雨に
わたしの 乾いた眼が濡れる
「からまつ」とひらがなで書いた方がいいなあ。春の展葉がきれいだなあ。秋の金色がきれいだなあ。このからまつの美しさをよく知って書いたのは串田孫一ですね。さすがです。
秋の金色になりつつある葉を摘んでお茶にして飲んだことがあります。からまつ茶です。ちょっと湯につけるときれいな渋めの黄色になります。深い秋のにおいがしました。大地の香りがしました。ふかふかになったからまつの林の道を歩く自分がよみがえります。
山と文学-串田孫一のことば-

夏,涸沢へ
山歩きが好きな人は,何度も山を振り返って歩いてきた稜線や山並みや道をしみじみと見つめながら下りてきます。この時の感慨は一体何だろうと思います。懐かしいような,少し哀しいような気持ちになります。その山の印象を心の中に落ち着かせるのにしばし時間(とき)が必要なことは誰しも感じることだと思います。しかし,心の落とし処に収まった時にはもうすっかり別のものに変わっていることが殆どです。あの山で直接に感じた大切なものが抜け落ちてしまっていることが多いからです。そのような気持ちを串田孫一はこう語ります。
私の頭の中で山が抽象化される。それをここに文字にすれば,既に山の抽象は崩れる。仮に抽象画家が絵にしても姿は代わる。すべて芸術以前の,音も形もない,また動きもないものである。
「白と緑」から,『心の歌う山』所収
注意せよ。諸君。山の印象はあなたの中でまたたく間に変わる。頭の中で,そして文字にするとなおさらのこと・・・。なぜこれほどに山から下りてきたときのあの正直な感慨に気を付けなければいけないと串田孫一は言うのでしょうか。また人の心は移ろいやすく,すぐ見てきたことや感じたことを勝手に,手前みそに納得することに注意深くなくてはいけないと彼は言うのでしょうか。そこに詩人としての串田の譲れない立ち位置(スタンス)というものがあると思います。自然からのすべての恵みを「あなたには正しく受け取ってほしい」という気持ちが伺えるのです。その裏には人間の理解というものがどれほど曲解されているかという危惧感が串田にはあるようです。
ミズバショウ咲く季節
では,感じた自然をいつも勝手に変えてしまって,本当の姿を私たちは知り得ないというのでしょうか。そんなことはありません。
より細かいものが次々に見えて来ること,私の方から言えば注意深く観測しようとすること,そしてそこにかくれたものを見つけ出す悦びと,今度はそれとは凡そへだたりのある抽象とは,どうも,ある時期に,全く予期しない時に私が襲われる愛情の動揺のように思われる。
人は本質を自分勝手に変えることに注意すれば自然の本来の姿を理解することが出来る。抽象化する行為も愛情のひとつであり,動揺という振幅のなせるわざであると彼は言います。そして彼は最後の文章でまとめる。
愛するものをもう一度考えて見ること。くりかえし考えてみること。これは実験である。芸術以前の静かな実験である。
この「白と緑」という文章は彼の著作の中では特別なものでもなく書き連ねられた断想のひとひらに過ぎません。しかし難解だと思われる彼の文章にしてははっきりと自分の自然に対する姿勢が書かれています。文の最後に,書かれたのが1957年4月とあります。1915年(大正4年)生まれの串田孫一が41歳の時の文章です。
涸沢岳から槍を望む
串田孫一の41歳というと,1957年のこの年は東京外国語大学で講師を始めて7年目。処女詩集『羊飼いの時計』を出して4年目,詩集を出す前の年に詩誌『アルビレオ』を刊行しています。「白と緑」を書いた3か月後,『まいんべるく』刊行に携わっている時期ですから,いよいよ彼の本領が発揮されている油の乗りきった頃の文章です。
栗駒山千年クロベ
なぜ私は串田孫一に惹かれるのでしょう。彼の本も少しは持っていて,山のことを考えたいときには彼の本を数冊出してきて,頁をめくっています。
多分,彼の自然に対する真摯さ,自然という自分を取り巻く世界への誠実さが魅力なのでしょう。しかし,彼の詩や文章は難解です。分かったためしがありません。それは彼のことばが,目的のために書かれることばではなく,また人を説得するために起こされる文章でもないからです。まさに彼は,山歩きからもたらさせれた恵みを芸術以前の実験の場で忠実に記録しようとする律儀さに満ちています。人の勝手な思考を極力抑えて対象に近づく「生の世界」を指向しているわけです。彼は山歩きをする詩人なのです。
笠ヶ岳夕景
これから不定期ながら「山と文学」と称して,心に浮かんだことを何回かに分けて書いていきたいと思います。まず串田孫一のことを取り上げながら進めていきます。でもうまく言えるかどうか分かりません。私自身はいつもメモなしで即興で書いているものですから。分かりにくいところはご容赦ください。
今日の本
心の歌う山 (1974年) - 実業之日本社,昭和49,1974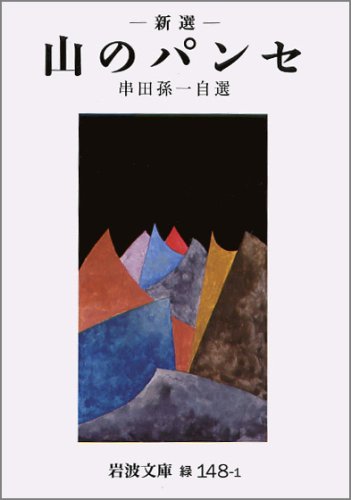
山のパンセ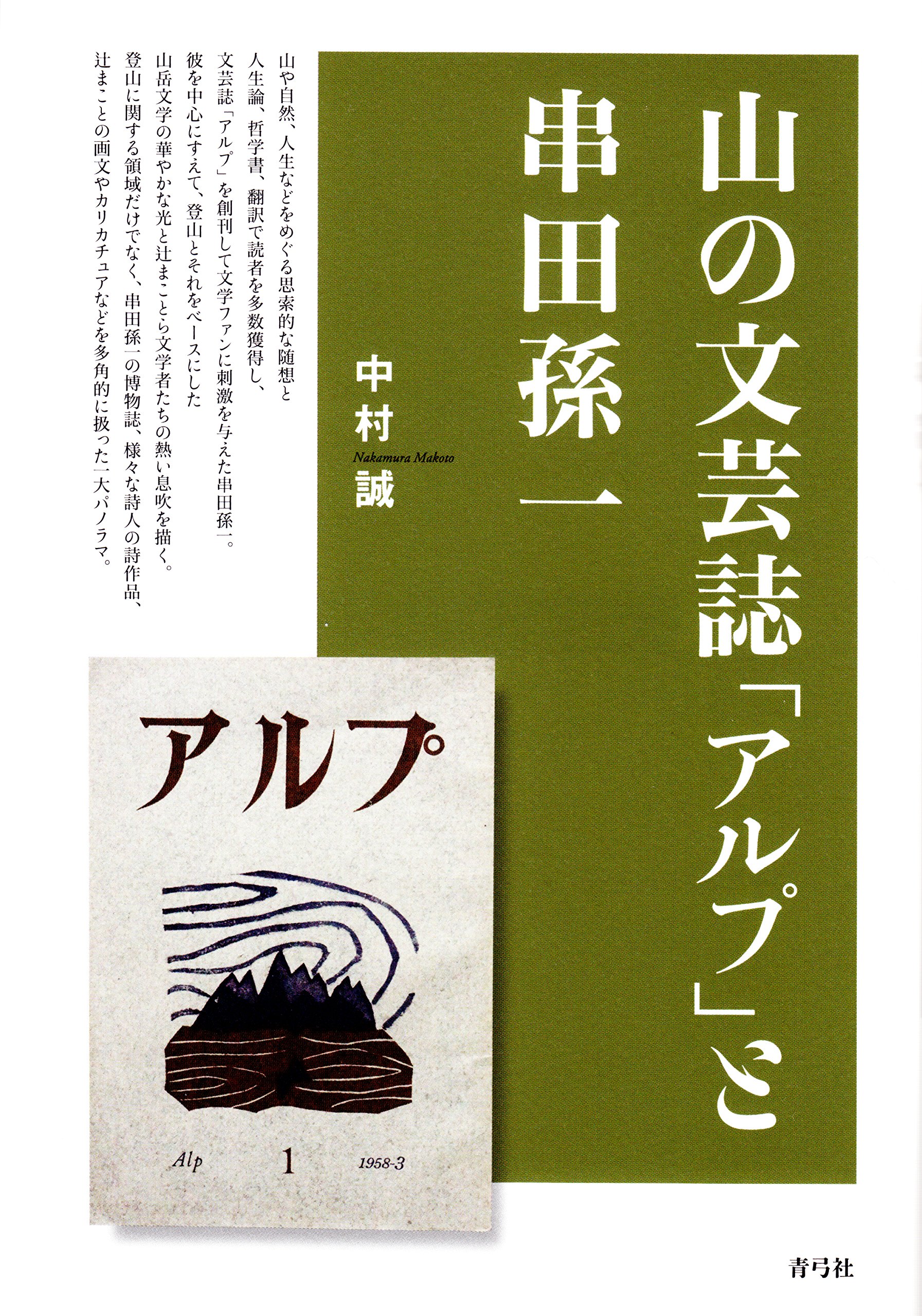
山の文芸誌「アルプ」と串田孫一
Eの糸切れたり
串田孫一の日記

栗駒山霧の朝の日の出
串田孫一は1915年(大正4)の生まれだが,『日記の欺瞞』という文を読むと1924年の正月から日記をつけ始め,死ぬまで日記を書いていたようだ。9歳から日記を書いていたことになります。そして「現在92冊目の帳面に書いている」とあるから死ぬまでには100冊を超えるノートにその日に感じた事々を記していたと思われます。
その串田が山へ行ったときにどんな記録を取っていたかは,彼の山歩きを知る上では大切なことでしょう。なぜなら彼の著作は日記の記録を起こすところから始まっていることはかなり確からしく感じます。串田自身が戦後まもない時期の28冊目から29冊目の日記をそのまま出版するということまでしているし,読書では様々な人の日記を興味深く読んでいる様子もうかがえます。
しかし作品を読むと,山に行った日付や時刻や費やした時間などの記録のほとんどが抜け落ちて,その山で感じた小さなことに紙面を費やして終わっていたりします。あえて書かないのでしょうか。どうも彼は山について感じたこと,景色から連なった連想,突然に湧き上がってきた断想などに悦びを感じているところがあります。
では山でもそんな記録の取り方だったのでしょうか。
ちがうようです。
蕪栗沼の朝
彼は1978年の覚書(『Eの糸切れたり』所収)で,山行の記録を次のように言っています。
天気図,雲の種類,雲量,雲向,風向,風力,降水量,気温などを記し,動植物その他の記録ももっと詳しく書いていた。一日も欠かしていない
となると重要な記録はすべて取っていたようです。特にと言っているので山行ではこのうち抜けている記録もあると思いますがかなりの記録です。こんなに記録を取っておいているのに,作品ではいきなり「あの朝は」で始まり,日付も,時刻も,天候もわからないように作品は進むのです。
蕪栗沼の朝
彼は記録の中から,すべてをそぎ落として残ったものの中にその山行の印を見いだそうとするかのようです。すべてをただ書き連ねることをよしとしません。その山が彼自身にもたらした感覚や徴(しるし),突然湧き上がってきた記憶,心の底から見いだされたことば,花,なんでもない出来事こそが彼の山登りなのです。
そんなところに串田孫一のスタイルが見いだされます。